はじめに
理学療法の臨床では、「この痛みの原因はどこか?」「なぜこの動作で症状が出るのか?」といった構造と機能のつながりを見抜く視点が求められます。
そんな臨床推論に迷いがある方にこそ読んでほしいのが、林典雄先生の
『運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈』シリーズ(上肢編・下肢編)です。
書籍概要
- 書名:運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 上肢編/下肢編
- 著者:林 典雄(理学療法士/治療家・講師として全国で講演多数)
- 出版社:運動と医学の出版社
- 判型/頁数:A4判・フルカラー・約200ページ超
- 特徴:臨床に即した“機能解剖に基づく評価プロセス”を症例と図解で学べる
《上肢編》の内容詳細
1章:機能解剖の基礎
- 上肢帯(肩甲骨・鎖骨・胸郭)の立体的な構造
- 肩甲骨の可動性と安定性のバランスとは何か
- ローテーターカフと肩関節中心軸の関係性
第1章では、肩甲骨や鎖骨・胸郭といった肩甲帯の立体構造が詳細に解説されており、解剖学の再学習だけでなく、触診技術や動作観察の基礎固めとして活用できます。
新人セラピストや学生の教材にも最適です。
2章:肩関節周囲の評価と解釈
- インピンジメント症候群の分類と見極め
- 肩峰下空間の狭小化を生む要因の多角的評価
- 棘上筋 vs 三角筋の筋力低下の見極め
- 上腕骨頭の偏位と腱板断裂の関係性
第2章では、腱板損傷やインピンジメント症候群といった臨床頻度の高い疾患をテーマに、どの構造がなぜ関与するのかを論理的に追う評価法が展開されています。
痛みの出る部位を“結果”ではなく“原因”として捉えたい方には、仮説・検証の思考トレーニングとしても有用です。
3章:肩甲胸郭関節と動作分析
- 肩甲骨の下制・前傾がもたらす代償動作
- 「ウイング」現象の評価と原因の見立て
- 頚椎・胸椎アライメントと肩甲骨運動の関係
第3章は、肩甲胸郭関節の動きに着目し、猫背・巻き肩・肩甲骨のウイングなど、姿勢由来の運動障害を構造的に読み解く視点が満載です。
評価に苦戦する「姿勢アライメント」が、手順を追って可視化されます。
4章:肘・前腕・手関節の機能評価
- 外側上顆炎(テニス肘)に関与する筋群と肘伸展位の動作分析
- 手関節周囲の安定化に関与する筋・靭帯・骨配列の評価方法
第4章では、外側上顆炎や円回内筋症候群など、手・肘の評価において見落とされがちな構造を丁寧に紹介しています。
上肢遠位部の“隠れた原因”を探す再評価の視点としても活用できます。
《下肢編》の内容詳細
1章:骨盤・股関節の機能解剖
- 骨盤の前傾・後傾と大腿骨頭の支持関係
- 股関節屈曲制限の背後にある「関節包の緊張」と「腸骨筋の短縮」
- 中殿筋の支持機構とTrendelenburg徴候の読み方
第1章では、骨盤と股関節の位置関係や支持構造を通して、中殿筋・腸腰筋の触診評価や筋機能の推定が学べます。
片脚立位が不安定な症例や歩行中の骨盤の動揺評価の裏付けとして非常に有用です。
2章:膝関節と膝蓋骨の評価
- 膝蓋下脂肪体の圧痛と滑走性障害の評価
- 内側広筋と外側広筋の活動バランスが及ぼす膝蓋骨の追従性
- 膝蓋骨外方偏位と大腿骨遠位の捻転アライメント
第2章は、膝蓋下脂肪体や膝蓋骨の偏位に着目し、膝蓋大腿関節の構造的ストレスを可視化する評価手順が学べます。
画像所見が得られないケースでも、痛みの本質を“動き”と“触診”から導く方法を提示しています。
3章:足部・距骨下関節の構造と臨床応用
- 足部アーチと踵骨の傾斜角度が支持性に与える影響
- 回内足が膝・股関節に及ぼす連鎖評価
- 距骨下関節の“可動性の過剰”と“固定性”の鑑別
第3章では、距骨下関節や足部アーチの安定性に注目し、足部由来の代償運動や上行性の運動連鎖を整理できます。
回内足や扁平足の患者に対して、足部から全身の動作を見直す視点を得るのに最適です。
4章:歩行と動作分析への応用
- 荷重応答期における足関節〜骨盤の連鎖的代償
- 立脚中期での内転筋の関与と体幹側屈の出現
- 階段昇降・片脚立位の痛みから読み解く部位特定法
第4章は、歩行や階段昇降、片脚立位などの動作に潜む疼痛誘発要因を、構造と運動パターンの関係から読み解いていく構成です。
実際の動作場面を観察しながら、どの関節構造が痛みに関与しているかを仮説検証できる資料として活用できます。
林典雄シリーズが支持される3つの理由
理学療法士向けの参考書は数多くありますが、その中でも『運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈』シリーズは、発売以降、全国のセラピストから圧倒的な支持を集めています。
では、なぜここまで高い評価を得ているのでしょうか?
その理由は、次の3つに集約されます。
理由①:圧倒的にわかりやすい図解と構造の見せ方
本シリーズでは、臨床解剖を立体的に理解できるよう、関節・筋・神経の位置関係が丁寧に図解されています。
特に、触診すべき位置・アプローチの方向・関節包や脂肪体の描写など、教科書では得られないリアルな情報が満載です。
視覚から理解することで、評価や手技の精度が一気に向上します。
- フルカラーの詳細イラスト
- 臨床写真付きで“触れる位置”が明確
- 関節の奥行き・深さを意識できる解剖構成
理由②:「どう評価し、どう解釈するか」が一貫して学べる
本書はただの解剖書ではありません。
“症状にどうアプローチすべきか”という臨床推論の流れが、各章で一貫して構成されています。
症状の観察から始まり、構造の仮説、評価、そして治療戦略まで、まるでカンファレンスのように論理展開されており、実際の現場でそのまま使える思考手順が身につきます。
- 観察 → 仮説 → 評価 → 解釈 → 治療の臨床プロセスを明示
- 思考が迷子にならない「臨床的な道筋」
- 新人からベテランまで応用可能な構造的ロジック
理由③:すぐに臨床に落とし込めるリアリティと再現性
本シリーズの魅力は、「あ、これ、うちの患者さんにも当てはまる!」と読んだその日から使える実践性の高さです。
構造と機能を結びつけた内容は、表面的な知識にとどまらず、現場での再評価や指導にも直結します。
さらに、どの章も臨床現場の“あるある”をベースに構成されているため、読者自身の症例とリンクしやすく、記憶にも残ります。
- 典型例ではなく「実際にあるケース」に基づく解説
- モデル症例で学びながら再現性を高められる
- 教育・勉強会・後輩指導の教材にも最適
こんな人におすすめ!
- 動作観察と評価のロジックを深めたい新人PT
- 解剖学的知識を臨床で使いこなしたい中堅PT
- 症状の“背景にある構造”を探るのが好きなベテランPT
おわりに
林典雄先生のシリーズが評価されているのは、単なる知識の提供ではなく、「その知識をどう使うか」までを教えてくれる実践書だからです。
理学療法士として「診る力」「考える力」「伝える力」を磨きたい方には、必携の一冊となるはずです。
知識を“理解”だけで終わらせず、“使える知恵”に変えていくための良書として、ぜひ臨床に取り入れてみてください。




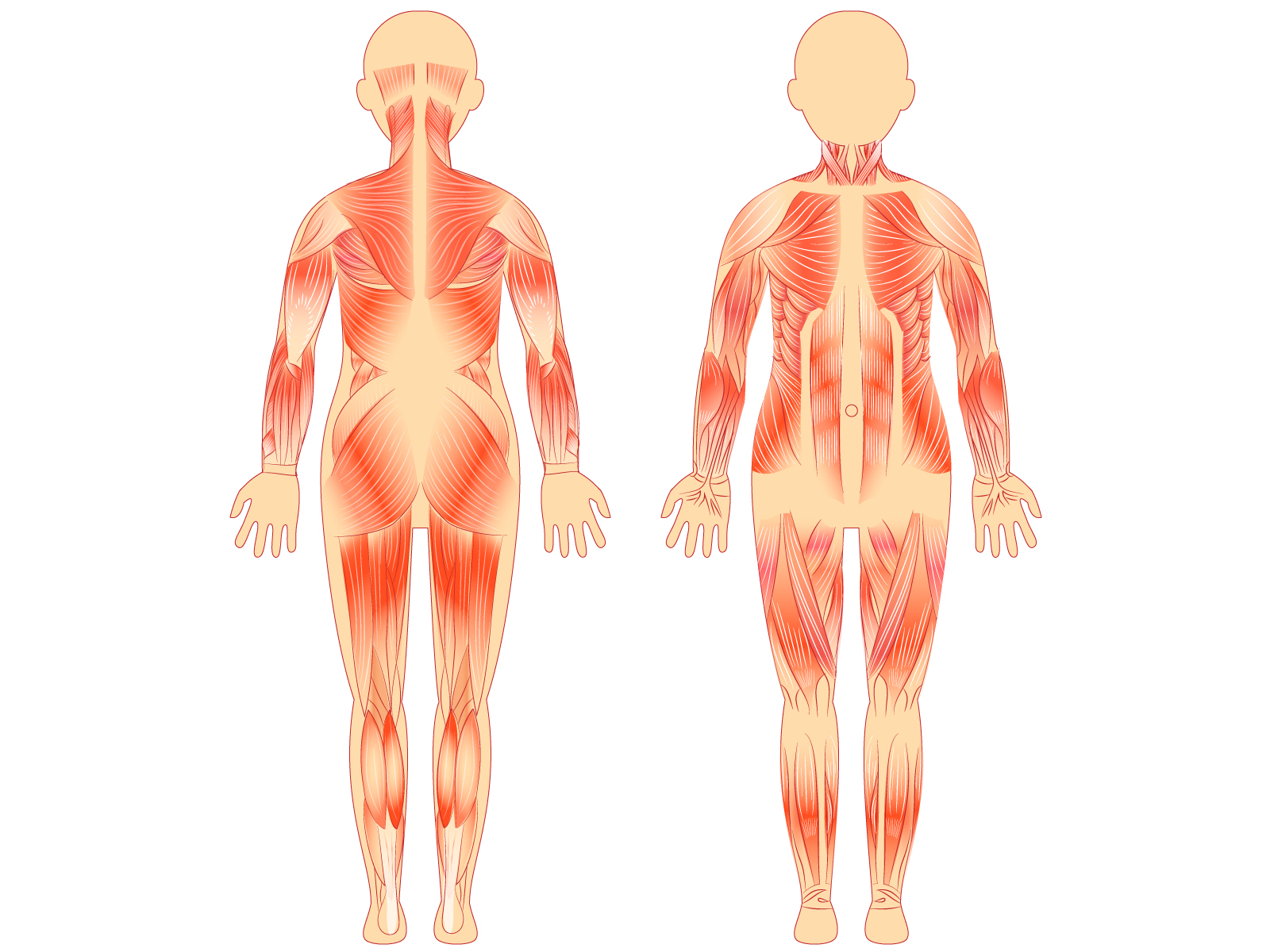


コメント